1 はじめに
講師の先生は、養護学校の教諭・教頭・校長として長い間ハンデイのある子達の成長 を願い実践されてきた、特殊教育のプロフェッショナルです。定年後、いまの高校で校 長としてご活躍をされています。
2 人の発達のプロセス
○子どもの成長を安定させるもの
・知的な安定(知能)・身体の安定(運動)・情緒の安定
・人に対しての興味関心を持つ(社会性)
○人間はみんな良さを持っている、個性を持っている。(個性を大切に)
講師の好きな詩 『私と鈴と小鳥』 金子みすず
○田口 恒夫
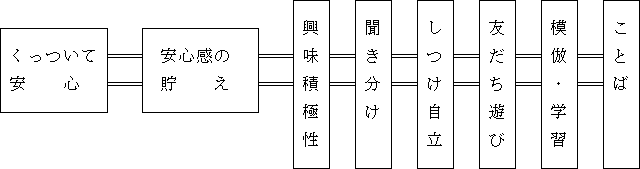
◎母がいると安心⇒安心感を持たせる⇒好奇心が強まる⇒いろいろなことをしてみたい
→ 成功を得る ×あれをやったらダメ(母はこわいもの)
3 いま、子どもたちの間に起きている問題
○心の交流がなくなってきた(友だちとのやりとりができなくなってきた)
いろいろな要因がある。
○生活様式が変わってきたために
・雑巾がしぼれない ・はしが使えないなど
4 どのような子どもであって欲しいと願っているか
○「健康で、明るく、思いやりがあって、よく勉強のできる親の自慢できる子」
上記に近づけるのに必要な要件
(1)健康な出産 (2)健全な家庭 (3)適度の働きかけ
(4)基本的信頼の確立 (5)諸々の経験拡張 (6)認める、称賛する
5 「学習障害」の教育
○星槎国際高等学校(芦別市にある私立の高校)の教育
・不登校や学習障害児たちもいっしょに一人一人面接し、その子たちがどういうところで生活しているのかを把握する。現在、旭川や帯広方面からも通ってきている。
・1週間で2回登校日がある(広域通信制)
・単位制(3年間で80単位)
・普通科
・9:00〜11:00フリータイム 11:00〜16:30授業
☆教育目標
・一人で生きていける勇気と自信を育てる
・個性を大切にした体験重視型の教育を行う
・断片的知識をではなく総合学習により生きる力をつける
・社会適応技術(SST)を高める指導を行う
○1週間に2日の登校以外の日は生徒は、アルバイトをしたり、学校で経営している学 習塾(教育研究所ペガサス)に通っている。
6 おわりに
○講師の思い
・LDの子どもにして良いことは、普通の子にして良いこと
・LDの子どもにして悪いことは、普通の子にして悪いことでないかと考える
講師の先生のお話をお聞きすると、星槎国際高等学校では半数の生徒が精勤賞であり、1割が皆勤賞という。子どもたちが本当に高校生活を楽しんでいることがわかった。私も、教師生活のはじめが、私立の高校であったため、昔を振り返り、校則・規律を重んじるばかりに生徒の前では自分らしさも出せず、何もしてあげられないまま学校を去っていく生徒がたくさんいた。本当に何のために教師になったのかと悩む毎日だった。仕事と部活の指導に終われ、子ども一人一人に目を配ってやれなかったことを今でも悔やんでいる。こういった星槎国際高等学校のような理念の学校がたくさんできると詰め込み教育といわれる日本の教育も変わり社会も変わっていくのではないかと思う。